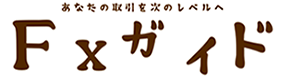FOMCが重視する主な経済指標とその見方
FOMCが重視する主な経済指標とその見方
1. 消費者物価指数(CPI)
-
内容:一般家庭が購入する財やサービスの価格動向を示す物価指標。食料・エネルギーを除いた「コアCPI」がインフレの基調を示すものとして特に注目される。
-
見方:FOMCは、物価安定の目標である「2%インフレ」を達成できるかどうかを確認するために重視。コアCPIが高止まりしている場合、利下げは難しく、逆に鈍化すれば金融緩和に動きやすい。
2. 個人消費支出物価指数(PCE)
-
内容:米国の家計が実際に購入した財やサービスの価格変動を測定する指標。FOMCが公式に「物価目標の基準」としている。コアPCE(食料・エネルギーを除く)が特に重要。
-
見方:CPIよりも幅広い支出項目をカバーしており、変動も安定的。FOMCは特に「コアPCEインフレ率が2%に向かって低下しているか」を注視する。
3. 生産者物価指数(PPI)
-
内容:企業が仕入れる段階での財やサービスの価格を示す指標。消費者物価に先行する動きを見せることが多い。
-
見方:PPIが上昇すると、将来的にCPIやPCEに波及する可能性があるため、インフレ圧力の先行指標として利用される。
4. 雇用統計(BLS発表の月次雇用レポート)
-
内容:非農業部門雇用者数、失業率、平均時給などを含む米国の主要な労働市場指標。
-
見方:雇用の増減は景気の強さを反映し、平均時給の伸びは「賃金インフレ」につながるため重要。強い雇用は利上げを後押しし、弱含むと利下げ観測が強まる。
5. JOLTS求人件数
-
内容:米国における未充足の求人件数を示す。労働需要の強さを測る指標。
-
見方:求人が多ければ労働市場の逼迫を示し、賃金上昇圧力=インフレ要因となる。求人件数が減少すれば労働市場の過熱感が和らぎ、利下げ観測が高まる。
6. GDP成長率
-
内容:米国の経済規模の拡大ペースを示す指標。四半期ごとに発表され、実質GDP成長率が注目される。
-
見方:潜在成長率(約1.8〜2.0%)を大きく上回れば景気過熱と見なされ、インフレ懸念から利上げ圧力となる。逆に低迷すれば利下げの根拠になる。
7. ISM製造業・非製造業景況感指数
-
内容:企業の購買担当者に景況感を調査した指標。50を上回れば拡大、下回れば縮小を意味する。
-
見方:企業活動の先行きを示すため、FOMCは景気後退リスクを測る上で重視する。
8. ミシガン大学消費者信頼感指数
-
内容:消費者の将来に対する景気・物価見通しを調査したもの。
-
見方:インフレ期待を測る重要な指標。長期的なインフレ期待が高まれば、FOMCは金融引き締めに慎重さを欠けられない。
まとめ
FOMCは「雇用の最大化と物価の安定」という二重の使命を担っており、物価関連では特に コアPCE、労働関連では 非農業部門雇用者数や賃金動向 を最重要視します。さらに、先行指標であるPPIやISM、景気循環を示すGDPも参考にしながら総合的に政策判断を行っています。